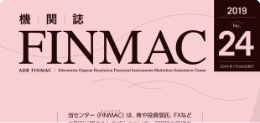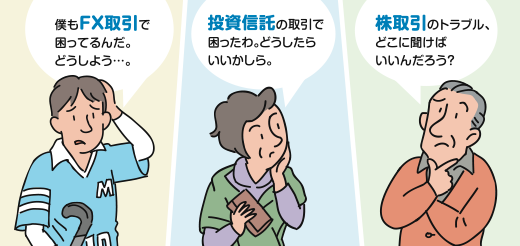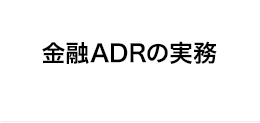紛争解決等業務の質の向上への取組み
当センター、
1.紛争解決委員(あっせん委員)の選任について
あっせん手続は、公正・中立な立場にある紛争解決委員(あっせん委員)の立ち合いの下で、当事者間の話し合いにより紛争を簡易・迅速に解決しようとする仕組みです。
あっせん手続を担当する紛争解決委員(あっせん委員)には、金融商品に関する紛争の解決に有用な知識経験等を有し、かつ、公正・中立な立場にある弁護士を選任しています。(全国で38名。東京、大阪、名古屋などの9地区に分けて選出)
紛争解決委員(あっせん委員)の選任は、その職務の重要性にかんがみ、次のような手続を経て行っています。
- (1)あっせん委員候補者推薦委員会(有識者3名)による推薦
- (2)運営審議委員会における審議
- (3)理事会決定
- (4)理事長による委嘱
紛争解決委員(あっせん委員)の任期は1年で、その再任の適否についても、あっせん委員候補者推薦委員会において、あっせんの実施状況、年齢、在任年数等を総合勘案して、審議しています。
紛争解決委員(あっせん委員)の氏名は、当センターのホームページ上で公表しています。また、当センターの機関誌に「あっせん委員の眼」のコーナーを設け、あっせん委員からの寄稿を連載しています。
個々の事案を担当する紛争解決委員(あっせん委員)を指名する際には、その事案に特別の利害関係を有するあっせん委員を排除する仕組みを設けています。
2.相談員及びあっせん委員の資質、能力向上への取組み
当センター、
- (1)相談員研修の実施
相談、苦情、あっせん申立ての受付を担当し、あっせん手続においてあっせん委員を補佐する相談員に対して、原則として毎月一回研修を実施しています。具体的には、新たな法令・自主規制ルールに関する知識の習得や、利用者との電話、面談等におけるコミュニケーション能力の向上のため、外部講師を招いて研修を実施するとともに、相談、苦情等への対応の在り方について、個別の事例を踏まえた意見交換を行っています。
- (2)あっせん業務研究会の開催等
毎年一回以上、あっせん委員による懇談会(あっせん業務研究会)を開催し、法令等の改正やあっせん申立ての動向の説明のほか、具体的なあっせん和解事例について事例研究を行うとともに、あっせん手続の進め方に関する諸問題(特別調停案提示の在り方を含む。)について、あっせん委員間での意見交換を行い、他のあっせん委員との情報の共有化を図ることにより、あっせん手続の改善に役立てています。また、あっせん終結事例の概要情報をあっせん委員全員に送付し、紛争解決の促進や同じ目線でのあっせん手続の実施に役立てるようにしています。
- (3)相談員とあっせん委員との意見交換会の開催
当センターの相談員は、あっせん手続において、あっせん委員を補佐する役割もあります。このため、相談員とあっせん委員との間の意思疎通の緊密化を図ることが、迅速な紛争解決につながることから、相談員とあっせん委員との意見交換会を開催し、苦情解決支援及びあっせん手続における相談員の役割、対応の在り方等について意見交換を行っています。
3.外部有識者の意見を反映させる業務運営
当センター、
外部有識者の意見を取り入れて講じた主な施策は次のとおりです。
・ホームページの充実
・あっせん委員候補者推薦委員会の設置
・あっせん手続利用者に対するアンケート調査の実施とその活用
・通貨オプション事案の増加に対する対応
4.利用者アンケート調査の実施とその活用
当センター、
アンケート調査は、あっせん手続が終結した段階で、双方の当事者(顧客及び金融機関)に対して、和解、不調のいかんを問わず、行っています。
アンケート調査の回答結果については、あっせん委員懇談会(研究会)や運営審議委員会、理事会等に報告するほか、今後のあっせん手続の改善に役立てることとしています。
平成26年10月から平成27年9月までの期間の回答結果の概要について、機関誌(FINMAC)第17号に掲載しています。
5.他の金融ADR機関等との連携
当センター、
他の金融ADR機関で取り扱うことがふさわしいと考えられる事案についてご相談があった場合には、他の金融ADR機関を紹介することとしています。
以上のほか、全国の消費生活センターから、証券取引等に関する制度の内容や紛争解決を図る上の留意点などについて、日常的にご相談を受け、それぞれの機関における消費者の方々への対応に役立てていただいています。また、国民生活センター、全国消費生活相談員協会、東京都消費生活総合センター等との機関とも、随時、意見交換を行っています。
法務省の認証を受けているADR機関が参加する日本ADR協会に加入し、同協会でのセミナーに参加するなどの活動も行っています。
6.業務運営の重要事項
当センター、
- (1)相談、苦情処理及び紛争解決業務の公正中立な運営
- (2)あっせん委員及び相談員に必要な専門知識及び能力の向上
- (3)相談、苦情処理及び紛争解決の動向等に関する情報の開示
- (4)他のADR機関や自主規制機関等との緊密な連携
- (5)話し合いによる紛争解決等の仕組みや
FINMAC に関する普及啓発・周知活動の実施 - (6)業務の質の向上に向けた継続的な取組み
株式、債券、投資信託、
FXなどのトラブルでお困りの⽅、
お気軽にご相談ください。

こんな記事も読まれています